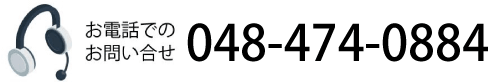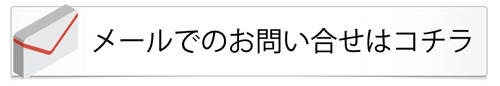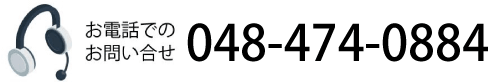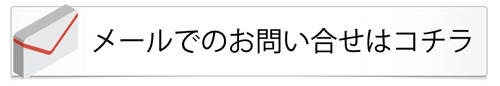犬の肝臓に発症する病気にはどのようながあるのでしょうか。
犬の肝臓疾患のうち、腫瘍(肝臓がん)以外の主な疾患について、肝臓病になる原因や現れる症状、治療法などをまとめました。
もし肝臓病になってしまったとしても肝機能改善のために国産SPF豚由来プラセンタキス末を利用したり、免疫調整機能が期待できるコルディを利用することで肝機能が改善する可能性もあると考え研究を進めております。
目次
犬伝染性肝炎(犬アデノウイルス1型感染症)
ワクチン未接種の子犬では致死的な症状を起こすことがあり、突然の虚脱(極度の脱力状態や急激な意識障害)、突然死を呈する事があります。
成犬では無症状のまま耐過することが多いです。
犬伝染性肝炎の症状として、肝臓が炎症を起こすことにより発熱が数日続き、鼻汁や発咳、食欲不振などが見られます。
重症では発熱による肝機能障害、肝機能低下が進行します。
消化器症状として下痢や嘔吐、腹痛などが挙げられますし、東洋医学では肝臓は目と関連しているため、目やにや結膜炎、前部ぶどう膜炎なども併発します。
また、肝臓の腫大が起きることで血液やリンパの循環、胆汁の排泄阻害が起こることから、黄疸や腹水なども引き起こします。
回復期に移行するときには、犬伝染性肝炎で特徴的な「ブルーアイ」という角膜が青白く混濁した状態が数週間続きます。
この混濁は回復する場合もありますが、残ってしまう場合もあります。
治療法
犬伝染性肝炎の有効な治療薬はありません。
インターフェロン等の非特異的抗ウイルス剤でウイルスを抑制したり、肝臓の機能を補うためのタンパク質やビタミンなどの点滴(補液)を行います。
また、細菌による二次感染を防ぐために抗生剤の投与も行われます。
食事療法として、肝機能をサポートする食材を取り入れる事は是非ともお試しいただきたいと思います。
予防法
ワクチン接種が有効です。
犬伝染性肝炎を引き起こす「犬アデノウイルス1型」は、混合ワクチンの3種~11種全てのワクチンに含まれています。
犬の急性肝炎
犬の急性肝炎は文字の通り、肝臓に急性の炎症が起きている状態を指します。
急性肝炎は、細菌などの病原体感染によるものと、外傷ができた時に化膿してしまった結果発症するものがあります。
どちらの病態にしても、下痢や嘔吐などの消化器症状が見られます。
黄疸や腹水、慢性肝炎へ進行する場合もあり、最悪の場合には昏睡を引き起こすこともあります。
治療法
急性肝炎になったときは輸液や抗生剤の投与で症状軽減をはかります。
その他、栄養補給や食事療法も合わせて行いつつストレスがかからないよう安静に過ごすことをお勧めします。
予防法
定期的な検診や、有害なものの摂取を避けること、ワクチン接種(アデノウイルスの予防)が挙げられます。
ただ、黄疸や腹水などの症状が見られた頃には肝臓障害がかなり進んでいる場合がありますので、嘔吐や下痢などの症状が出た際には、早めに受診することをお勧めします。
犬の慢性肝炎・肝硬変
この病態(慢性肝炎)が進行した場合、肺の組織が線維化することで肝線維症となります。
この状態が長期化して肝臓全体の構造が変化してしまった物が肝硬変です。
犬が肝硬変になると肝臓内の血流動態が滞るため、最終的に腹水や肝性脳症などの病態も引き起こします。
肝硬変はドーベルマン・ピンシャーやコッカー・スパニエル、ラブラドール・レトリーバーなど特定品種で多く発症する傾向もあり、ベドリントン・テリアに関しては遺伝的に銅の蓄積が認められます。
犬が肝硬変になっても無症状を呈することも多いですが、一般的には食欲低下や、嘔吐、下痢などが起こり、進行していくと黄疸や腹水貯留、出血傾向などが認められます。
また、肝機能が障害されることでアンモニアなど毒素の解毒を行うことができなくなり、肝性脳症などの神経症状も現れる事があります。
治療法
薬剤による慢性肝炎の場合には、減薬若しくは中止する必要があります。
副作用が強く現れてしまったり、効果が十分現れてこない場合には免疫抑制剤との併用により炎症を抑えます。
肝機能が低下することで腹水がある場合には利尿剤で水分排泄を促します。
その他、食事療法(肝機能をサポートする食材はこちら をご覧ください)としては、アンモニアの発生を減らす目的でタンパク質制限食が基本となります。
しかし、ワンちゃん・ネコちゃんは私たちよりも多くのタンパク質を必要としますので、タンパク質の分解産物であるアミノ酸のかたちで摂取できる(BCAA等)を利用すると良いと思います。
また、国産SPF豚由来プラセンタキス末の抗炎症作用により、症状を軽減する事も期待できます。
予防法
過剰な薬剤の使用、有害なもの(添加物など)の摂取を控え、肝臓に負担をかけないようにすることが大切です。
犬の門脈体循環シャント
シャントとは「短絡」のことで、本来消化管や膵臓、脾臓から肝臓に繋がる血管(門脈)が短絡血管によって大静脈に繋がってしまっている病気です。
本来肝臓に入って解毒するはずのアンモニアなどの毒素が、短絡血管によって解毒されずに大静脈に入り体の中を循環してしまうことで、毒素による障害を受けます。
場合によっては、肝臓にしっかりと血液を供給することが出来ないことから肝臓が十分成長できず、機能を果たさなくなるため、体自体の成長障害等も引き起こします。
短絡血管は肝臓の中(肝内)にあるものと、肝臓の外(肝外)にあるものがあり、肝内シャントは大型犬に多く手術が困難、肝外シャントは猫や小型犬に多く、シャント血管を特殊な器具で閉鎖する手術方法があります。
多くは先天性(生まれつき)のもので、発育不良や神経症状などを引き起こします。
- ミニチュア
- シュナウザー
- ヨークシャーテリア
- ミニチュア
- ダックスフント
- トイ・プードル
発症年齢は、生後4週齢から、男の子の場合には潜在精巣を併発している確率が多いと言われています。
食欲不振や元気消沈、下痢、食後の嘔吐や神経症状(ヨダレや徘徊、発作、痙攣)などが見られます。
重症の場合には死に至ります。
また、遺伝的な要素が指摘されているため、門脈シャントの遺伝子を持つ可能性がある犬は繁殖に使わないことも、予防策の一つと言えます。
後天性の門脈シャントは、肝硬変や肝線維症、慢性肝炎等の肝臓の障害や胆管閉塞などによって、肝臓に入る血液がうっ血することによって、門脈の血圧が上昇することで対象的に出現します。
典型的な症状を表さない場合でも、膀胱結石(血液中の過剰なアンモニアにより結石ができやすくなるため)による血尿や血液検査(肝臓の数値やアンモニアの数値、食前食後の総胆汁酸の数値)、レントゲン検査(小さな肝臓)などで異常に気づく事もあります。
超音波検査では非常に有効な検査ですし、CT検査でも門脈の評価が出来ます。
治療法
先述の通り、肝外シャントの場合には手術が有効な場合があります。
内科療法としては、肝性脳症を引き起こさないために、タンパク質制限食や抗生剤、ラクツロースなどでアンモニアの産生を抑えます。
後天性の場合には手術は適応外と考えられているため、門脈圧上昇の原因除去が重要となります。
食事療法として積極的に取り入れていきたい、肝機能をサポートする食材はこちらをご覧ください。
予防法
先天性の場合、遺伝性が指摘されているため、繁殖しないことで門脈シャントの子の拡大を防ぐことが出来ます。
後天性の場合には、門脈圧が上昇する原因が起こらないように過度な薬剤投与や有害なものの摂取、偏った栄養などのお食事の摂取を控えていくことが必要です。
また、好発犬種の場合には、定期的な検査で早期発見することも重要です。
犬の胆泥症、胆石症
胆汁を蓄えている「胆嚢」と言う部分に、胆汁由来の泥や石が溜まってしまっている状態を胆泥症・胆石症と言います。
犬の内分泌異常や、細菌感染による胆嚢炎、食事が原因となりますが、中には腸炎や膵炎・肝炎などから併発して胆嚢炎が起こり、そこから胆泥症・胆石症に進行することがあります。
犬に胆嚢炎が起こると、胆汁の組成が変化しカルシウムが結晶化して胆石症となったり、胆汁の粘稠性が増すことで泥となり胆泥症を引き起こす原因となります。
胆嚢炎、胆泥症、胆石症の症状として、犬の元気や食欲の低下、嘔吐、黄疸、便の色の変化(白っぽくなる)、時折腹痛を呈することもありますが、初期にはほとんど症状がありません。
その為、発見が遅れることが多く、最悪の場合には胆嚢破裂により腹腔内が汚染され、腹膜炎を起こすことがあります。
血液検査では肝酵素の異常や総胆汁酸の異常を示していることが多く、更にレントゲンやエコーなどの画像検査を行うことで、胆石や胆泥を検出することが出来ます。
犬治療法
無症状や症状が軽度の場合には、抗生剤や利胆剤(胆汁の分泌を促すお薬)などの内科的治療を行い、定期的にエコー検査を行い経過をみていきます。
内科的治療での反応が乏しい場合や、重症例、胆石の成分がカルシウム塩で内科治療が期待できない場合には、外科的治療を行います。
外科的治療の場合、胆嚢内の胆石や胆泥飲みを取り除く方法もありますが、再発の恐れがあるため、胆嚢ごと摘出する方法が一般的です。
食事療法では、間食や脂肪分の多い食事を控えること(低脂肪食)が推奨されます。
肝機能をサポートする食材はこちらをご覧ください。
予防法
定期的な検査での早期発見・早期治療や、幼いころからの適切な食事、運動が必須となります。
免疫力低下から胆嚢疾患を発症することも多いため、なるべくストレスを与えないような生活を送らせてあげることも重要です。
その他、内分泌の異常がある場合には胆汁の性状が変化しやすくなりますので、内分泌異常に対しての治療を行うようにしましょう。
胆嚢粘液嚢腫
胆嚢内に粘液が溜まり、胆嚢が拡張する良性の腫瘍で、高齢で、高脂血症を起こしやすいワンちゃん(ミニチュア・シュナウザーやシェットランド・シープドッグなど)で起こりやすい病気です。
細菌感染や炎症によって胆嚢内の環境が変わることで粘液が過剰に産生されます。
粘液によりゼリー状になった胆汁が蓄積することで胆嚢炎を起こしたり、胆汁の出口(総胆管)が詰まってしまうことで、黄疸を起こしたり、吐き気や元気食欲の低下、肝機能不全を引き起こします。
重症化すると、胆嚢壁が破裂、胆汁が腹腔内に漏れ出すことで腹膜炎を起こし、発熱、腹部疼痛、腹水、全身の虚脱が見られることがあります。
血液検査では、肝臓の数値の上昇や高脂血症、総胆汁酸数値の上昇、炎症マーカーの上昇が見られることが多いですが、確定診断のためにはエコー検査で胆嚢の画像を見ることです。
エコー画像でキウイフルーツのような模様や星状の模様が見られる場合には、胆嚢粘液嚢腫を疑います。
臨床症状を全く示さないことも少なくありません。
治療法
無症状や症状が軽度の場合には、抗生剤や利胆剤(胆汁の分泌を促すお薬)などの内科的治療を行い、定期的にエコー検査を行い経過をみていきます。
しかし、一般的にこの病気に関係した症状があるワンちゃんの場合には、手術による胆嚢の摘出が推奨されています。
術後の食事療法と内科療法の継続を行うことが重要です。
予防法
定期的な検査での早期発見・早期治療や、幼いころからの適切な食事、運動が必須となります。
免疫力低下から胆嚢疾患を発症することも多いため、なるべくストレスを与えないような生活を送らせてあげることも重要です。
肝臓は体内の中でも重要な臓器の1つです。
肝臓への負担を軽くすることで、ワンちゃん・ネコちゃんの健康維持も期待できます。
治療としても、予防としても食生活の改善は役立ちますし、そのサポートとしてプラセンタをご利用いただくこともお勧めします。
肝機能をサポートする食材を取り入れたり、国産SPF豚由来プラセンタキス末をご利用いただき、ワンちゃん・ネコちゃんの健やかな体作りを目指して頂きたいと思います。
犬の肝臓がん・肝臓病・肝硬変の対応策
犬の肝臓が心配な方、既に肝臓の病気を患ってしまっている方。元気食欲回復のためには国産SPF豚由来プラセンタキス末を1~2ヶ月与えることで良化する可能性がございます。
肝機能が改善すれば、少し量を減らしつつも国産SPF豚由来プラセンタキス末を続けていただくと、肝臓が元気になるだけでなく、皮膚の状態や毛並み・毛ヅヤが良くなってくると思います。
国産SPF豚由来プラセンタキス末やBCAA、クリルオイル(南極オキアミから抽出したEPA/DHAのオイル)についてご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
よくあるご質問
- 犬にとって肝臓はどのような働きをするのですか?
-
肝臓は、犬の体内で非常に多くの重要な役割を担っています。主な働きは以下の3つです。
- 胆汁の生成・分泌: 脂肪の消化吸収を助ける胆汁を作り、分泌します。
- 代謝: 食事から吸収された栄養素(糖質、タンパク質、脂質)を体が必要とする他の成分に変えたり、エネルギーとして利用できるように処理したり、貯蔵したりします。
血液を固めるために必要な「血液凝固因子」などのタンパク質も肝臓で合成されます。 - 解毒: 体内に入った薬や有害物質を分解し、無毒化します。また、タンパク質が分解される際に発生するアンモニアなどの有害な物質も解毒します。
これらの機能は互いに関連しており、肝臓の機能が低下すると、消化の問題、出血傾向、毒素の蓄積による神経症状など、体の様々な部分に影響が現れる可能性があります。
また、肝臓は口から入るもの(食事、薬、毒物など)の影響を直接受けるため、日々の食事管理や環境への配慮が肝臓の健康維持に繋がります。
- 愛犬に肝臓病の疑いがある場合、どのような症状が見られますか?
-
肝臓病の症状は、初期には分かりにくいこともありますが、病気が進行すると様々なサインが現れます。よく見られる症状には以下のようなものがあります。
- 元気がない、ぐったりしている
- 食欲不振、食べる量が減る
- 体重減少、痩せてくる
- 嘔吐や下痢、軟便
- 水をたくさん飲む、おしっこの回数や量が増える
- 黄疸(歯茎、白目、耳の内側などが黄色っぽくなる)
- むくみ(腹水などでお腹が膨らむこともある)
- 出血しやすくなる(鼻血、血便、皮下出血など)
肝臓の機能が著しく低下すると、体内で作られたアンモニアなどの毒素を解毒できなくなり、肝性脳症と呼ばれる神経症状(ふらつき、旋回運動、意識障害など)を引き起こすこともあります。
また、肝リピドーシス(脂肪肝)では肝臓の腫大が見られたり、胆汁の流れが悪くなると便が白っぽくなることもあります。
初期症状は元気消失や食欲不振など、他の病気と区別がつきにくい場合が多いため、「いつものことかも」と見過ごされがちです。黄疸などの分かりやすい症状が出る前に病気が進行している可能性もあるため、特に高齢犬や持病のある犬、特定の薬を長期服用している犬などは、定期的な健康診断と血液検査を受けることが早期発見に繋がります。
これらの症状が多岐にわたるのは、肝臓が体内で多くの重要な役割を担っているためです。
- 犬の肝臓病の原因は何ですか?
-
犬の肝臓病の原因は多岐にわたり、特定することが難しい場合も少なくありません。考えられる主な原因としては、以下のようなものがあります。
- 細菌やウイルスなどの感染症
- 特定の薬の長期的な投与による副作用
- 肥満
- 毒物(植物、化学物質、カビ毒など)の摂取
- 肝臓の腫瘍(がん)
- 事故などによる外傷
- 先天性の異常(門脈体循環シャントなど)
- 特定の犬種における遺伝的な素因(例:ベドリントンテリア、ウエストハイランドホワイトテリア、ヨークシャーテリア、ミニチュアシュナウザー、マルチーズ、シーズーなど)
このように、肝臓病は単一の原因で起こるのではなく、様々な要因が引き金となり得る複雑な状態です。そのため、診断には慎重な検査が必要となり、原因が特定できれば、それに応じた治療法が選択されます。
遺伝的な素因が疑われる犬種では、特に注意深い観察と定期的な健康診断が推奨されます。
- 犬の肝臓病はどのように診断されるのですか?
-
肝臓病の診断は、通常、いくつかの検査を組み合わせて行われます。まず、飼い主様から症状や既往歴などを詳しく伺い、身体検査を行います。その後、血液検査を実施して、肝臓に関連する酵素の数値や肝機能を示すマーカーを測定します。
血液検査で異常が見られた場合や、さらに詳しい情報が必要な場合には、レントゲン検査や超音波(エコー)検査などの画像診断が行われることがあります。これらの検査により、肝臓の大きさや形、内部構造、腫瘍の有無などを評価できます。慢性的な肝臓病や腫瘍が疑われる場合など、確定診断のためには、超音波ガイド下や腹腔鏡を用いて肝臓の組織の一部を採取し、病理組織検査(肝生検)を行うこともあります。
診断は、血液検査のような比較的負担の少ない検査から始め、必要に応じて画像診断や生検へと進められるのが一般的です。これは、肝臓病の原因や状態が多様であるため、段階的に情報を集め、他の病気の可能性を排除しながら、正確な診断を目指すためです。
監修獣医師:林美彩 所属クリニック:chicoどうぶつ診療所

代替療法と西洋医学、両方の動物病院での勤務経験と多数のコルディの臨床経験をもつ。 モノリス在籍時には、一般的な動物医療(西洋医学)だけでは対応が困難な症例に対して多くの相談を受け、免疫の大切さを痛烈に実感する。
ペットたちの健康維持・改善のためには薬に頼った対処療法だけではなく、「普段の生活環境や食事を見直し、自宅でさまざまなケアを取り入れることで免疫力を維持し、病気にならない体づくりを目指していくことが大切である」という考えを提唱し普及活動に従事している。
所属:
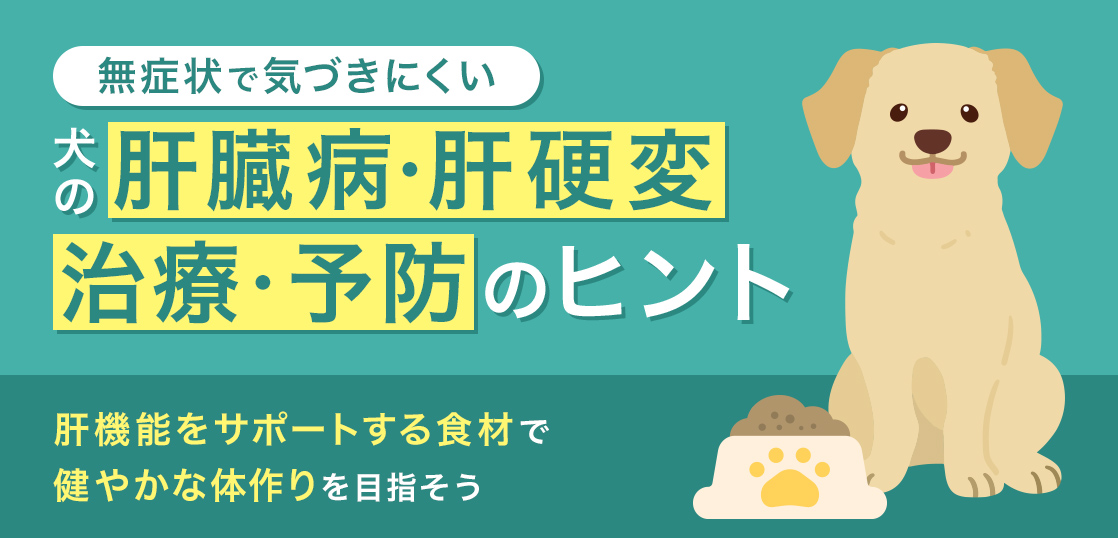
この記事が気に入ったら
いいね ! しよう