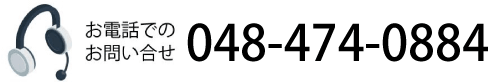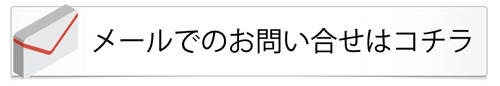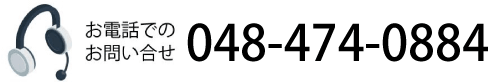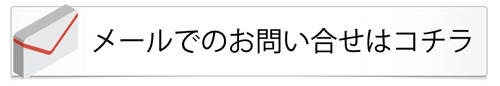犬が肝臓がんと診断されても悲観なさらないでください。
免疫の取り組みを行う事で体調が改善したりQOL(生活の質)を維持し元気食欲を回復させる事はできると考えています。
実際コルディで免疫対策をすることで犬のがんをコントロールできた例は多数あります。
このページでは肝臓がんの原因や症状、治療法、改善・完治のヒントなどをまとめました。改善例も多数紹介しています。
皆様の心の支え、希望の光となることができれば幸いです。
目次
犬の肝臓がん・肝細胞がん・肝臓腫瘍とは
皆様も一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれていて肝臓がんが発生していても初期の段階では症状として現れないため、発見も遅れがちです。
- 疲れやすい
- 元気がない
- 食欲がない
- 腹水が溜まってきた
- 肝臓の数値が悪くなった
これらの症状が現れた時は、既に肝臓がんが進行しているケースが多くなります。
肝臓がんの種類
原発性肝臓がん
犬の原発性肝臓がんは主に以下の4種類があります。
最も多いのが肝細胞がんで原発性肝がんの約半数は肝細胞がんです。
- 肝細胞がん:肝細胞が”がん化”して発生するがん
- 肝内胆管がん:胆汁の通り道である胆管に発生するがん
- 肉腫:肝臓の血管など間葉に発生するがん(血管肉腫、平滑筋肉腫など)
- カルチノイド:神経内分泌由来のがん
肝細胞がん
犬の原発性肝臓がんは、犬に発生する悪性腫瘍の中ではそれほど多くはありません。
原発性肝がんのうち肝細胞がんは、他の臓器に発生した”がん”が肝臓に転移するのではなく、肝細胞(肝臓の細胞)ががん化したものです。
犬の肝細胞がんは、原発性肝臓腫瘍のなかでは最も発生件数が多いと報告されており、単葉(肝臓の一つの部分)に孤立性の腫瘤病変を形成することが多いです。
そのため、肝細胞がんの治療の第一選択肢は外科手術です。
外科手術により、腫瘍を完全に切除できた場合の予後は比較的良好とされています。
ただ実際には、肝細胞がんを早期に発見することは容易ではありません。
その理由として、肝臓はとても大きな臓器であることです。
また、予備能力・再生能力の高い臓器でもあるので、「犬の様子がおかしい」と検査をして肝細胞がんが見つかったときにはすでに腫瘍が大きくなっていることが多いのです。
肝臓には多くの血液が流れ込んでおり、肝臓脈や門脈・大静脈などにがんが浸潤した場合は、腫瘍を切除するのは困難になります。
肝内胆管がん
犬が肝内胆管がんになるのは稀ですが、胆汁の流れがうっ滞(悪くなる)ため黄疸症状がでたり、下痢や便秘など便の状態が悪くなります。
数年前に女優の川島なお美さんが”がん”で亡くなりましたが、その時に患っていたのが肝内胆管がんです。
浸潤性の高いがんであるため、早期に発見し外科手術でがんを切除できたとしても再発・転移してしまうケースが多くなります。
また、抗がん剤も効き難い(ほとんど効かない)ため、一般に肝内胆管がんの予後は良くないと言われています。
血管肉腫
血管肉腫は、血管さえあれば場所を選ばずに発症する厄介なガンの一種です。
血管内に発症するため転移もしやすい病気です。
肝臓は多くの血液が流れ込む臓器で、肝臓内にはしばしば血管肉腫が発生します。
血管肉腫が大きく成長すると破裂して大出血を起こし、死に至る事もあります。
また一般に、血管肉腫の予後は宜しくありません。
平滑筋肉腫
筋肉というと腕や足などの運動時につかう筋肉(これを骨格筋といいます)を思い浮かべる方が多いと思いますが、血管や内臓を動かすのにも筋肉が必要であり、この筋肉の事を平滑筋と言います。
平滑筋は全身にあるため、平滑筋肉腫はさまざまな部位で発生します。
カルチノイド・神経内分泌腫瘍
カルチノイドは内分泌臓器のみではなく全身の臓器に発生します。
カルチノイドはとても転移しやすいがんなので、発見された時点で他の臓器に転移していることも少なくありません。
転生肝臓がん
例えば、胃や腸、胆嚢、胆管、膵臓などの内臓に発生したがんが転移する事ともありますし、乳腺腫瘍(乳がん)や肺がんが肝臓に転移することもあります。
血管肉腫やリンパ腫、骨髄腫、肥満細胞腫、メラノーマなどが肝臓に転移するケースも良くみられます。
これら他の臓器から肝臓に腫瘍が転移した場合は、転移性肝臓がんといいます。
肝臓がんの原因
原発性肝臓がんの原因
人間の場合、多くはB型肝炎やC型肝炎など肝炎ウイルスが原因となりますが、犬や猫では化学物質などが原因で肝細胞が炎症を来し発がんすることが知られています。
肝臓は体内の毒素を解毒する化学工場の役割をもっています。
農薬や薬剤(抗がん剤や抗生物質、ステロイドなどの長期使用)、防腐剤や着色料、保存料、塗料や化学薬品、排ガス、洗剤など体内にはさまざまな発がん物質が入り込んでくると肝臓が体内に入ってきた毒を無毒化しようとし一生懸命に働きます。
しかし発がん物質が慢性的に体内に入り込んでくると肝臓は炎症を起こしてしまいます。
慢性的な刺激・炎症は肝がん発症リスクを高めます。
タバコの煙が犬や猫のがんの発生率を高めているとの報告もありますので、喫煙者がいらっしゃるご家庭では注意が必要です。
これら化学物質が体内に入ると直ぐにがんになるとは言えませんが、長期にこれら化学物質にされされることは避けたいものです。
転移性肝臓がんの原因
転移性肝臓がんの原因は、初発のがん(原発のがん)がどこなのかによって異なります。
血流が滞っていたり体温が低いと転移しやすいので、身体を冷やさない事は大切になってきます。
肝臓がんの診断
検査には次のような項目があります。
- 血液検査
- 尿検査
- エコー検査
- MRI検査
- CT検査
- 腹部レントゲン検査
- 肝生検
肝臓にがんや他の病気があっても症状として現れにくいため、問診だけで肝臓の病気を判断することは困難です。
血液検査のうちALPやAST(GOT)、ALT(GPT)、γGTPなどの数値が異状値(高値)を示した時は、肝臓に何らかの病気がある可能性があるため、画像検査(エコー検査など)が勧められることがあります。
しかし画像検査を受ける際には鎮静剤などの投与が必要になる事があるので、本当に検査が必要なのか獣医師とよく相談されることをお勧めします。
肝臓がんの治療
肝臓がんが根治する可能性があるのは外科手術でがんを取りきることができた時です。
がんが塊を作っていて浸潤していない、かつ、一つの肝葉に限局しているような場合は、手術後の予後も良いため積極的に手術を受ける価値があると思います。
一方で複数の肝葉にがんが浸潤していたり多発しているようなケースでは、たとえがんを綺麗に切除したように見えても、たいていの場合は細胞レベルの取り残しがありますのですぐに再発してしまいます。
そのため多くのケースでは手術適応となりません。
肝内胆管がんは浸潤しやすいがんのため、外科手術後の再発・転移が短期間に高率で起こるため手術後の予後は宜しくありません。
もちろん、広範囲にがんが拡がっている場合は手術適応がありません。
カルチノイドも浸潤しやすいタイプのがんで早い段階からリンパ節や腹膜、肺などに転移しやすく一般に手術適応はありません。
手術
肝臓の一部にがんが限局している塊状型の肝細胞がんは、切除後の長期生存が期待できるため積極的に手術を受けることをご検討ください。
一方で、がんが複数の肝葉に多発していたり浸潤している場合は、広範囲の肝臓を切除する必要があるため(拡大手術)、身体への負担も非常に大きな手術を受けなくてはなりません。
たとえがんを切除できたようにみえても短期間で再発してしまう可能性が高いです。
そのため本当に手術を受けた方が良いのか慎重な判断が求められます。
手術を受けた方が良いのか、獣医師とよく相談されることをお勧めします。
抗がん剤治療
犬の肝臓がんに対して抗がん剤で治療を行う事もあります。
しかし、抗がん剤はがんを治すための治療ではなく、一時的にがんが縮小させることを目的に行う治療であることは忘れないでください。
肝動脈塞栓療法や肝動注化学療法などの治療を行う動物病院もありますが、いずれにしても抗がん剤治療でがんを完治させることは困難です。
抗がん剤治療を勧められたら、期待できる治療効果と副作用でQOL(生活の質)が悪化することはないのかをしっかりと確認し、「治療を受ける」 or 「受けない」のご判断をされることをお勧めします。
放射線治療
手術との併用や、放射線治療単独での治療で用いられることがあります。
ただ、放射線に対しての反応は個々によって様々ですし、全身麻酔を必要とする治療のため、麻酔薬によるお身体への負担は否めません。
老犬や肺に疾患のある犬の場合、麻酔のリスクは高まりますので慎重な判断が求められます。
肝臓がんの治療を受ける時に注意したいこと
手術も抗がん剤も放射線治療もメリットとデメリットがあります。
ご愛犬の状態を一番良く把握しているのは飼い主の皆様です。
獣医師に言われたから治療を受けたけど、治療を受けたら体調がかえって悪化してしまった、苦しみが多くなってしまった
という事にならないように、飼い主様が主体となりご愛猫のために治療を受ける・受けない・お休みするをご判断してあげてください。
抗がん剤治療を受けると決断したら、免疫対策のコルディと肝臓・腎臓のケアとして国産SPF豚由来プラセンタキス末で副作用対策をご検討ください。
肝臓がんに対する代替療法
多くの代替療法はお身体への負担が軽いため、同時にいくつかの治療を併せることも可能です。
身体へのダメージが少ないということは、病期や病態をあまり選ばないということです。
手術前や手術後の再発防止、手術できない症例、そして体力が低下している時でも多くの代替療法を行うことはできます。
特に次のような場合には代替療法を検討する意義は大きいと思います。
- 合併症が有り、一般治療ではリスクが高いとき
- がんとの共存を狙うとき
- QOL低下の回避を優先したいとき
- 確定診断が出る前
- 診断結果がどうも腑に落ちないとき
病院の治療と並行して代替療法を行う事も出来ますし、相乗効果も期待できますので、積極的に代替療法について考えてみてください。
肝臓がんのご愛犬の食事療法
私たち人間だけでなく、ワンちゃんのお身体も毎日のお食事で作られています。
お食事の見直し=体質改善にも繋がります。
免疫力を保てるようなお身体になるよう、日々のお食事をまず見直してみてください。
弊社では治療のベースとして栄養学的なアプローチを非常に重視しています。
がんが成長するためには糖質(ブドウ糖)が必要です。
そのため糖質をできる限り制限していくことは直ぐに始められ、身体への負担もなく、副作用などのリスクもありません。
一方で、食事療法はご家族の皆様の協力がなければ行うことができません。
適度なタンパク質を与えていただき、炭水化物・糖質が多く含まれれているフードの量を減らしていってください。
食事を変えるだけではがんは治りませんが、肝臓がんの成長に不可欠な糖質を制限することで進行速度を抑えることはできます。
フードを与えるだけよりも時間・手間はかかりますが、あまり難しく考えず始めていただければ幸いです。
肝臓がん・肝細胞がんを患ったときの食事療法
肝臓がんはブドウ糖を餌にして成長します。
そのため。普段の食事に含まれるブドウ糖の量をできるだけ減らしていく事で、がんの成長にブレーキをかけやすくなります。
また、BCAAなどのアミノ酸製剤を併用することで、肝臓に負担をかけること無く、不足分のタンパク質(アミノ酸)を補うことが出来ます。
肝臓がんの子にお勧めの食事について皆様の手間を少しでも軽減して頂きたく、食材リスト「ペットだって医食同源-がんに負けないための食材」を作成いたしました。ぜひご一読ください。
ご愛犬が肝臓がんを患ってしまったら免疫対策を
肝臓がんと闘うときに最も大切なことは、免疫を整えることです。
手術や抗がん剤治療を行う場合でも、あるいはそれらの治療ができない場合でも、免疫を整えることはご愛犬の予後改善にプラスになります。
犬も人間も免疫がしっかりしていなければ様々な病気になってしまいます。がんについても同じです。
肝臓がんに限った事ではありませんが、犬や私たちの身体には毎日がん細胞が発生しています。
そのがん細胞を見つけ出し、攻撃し、がんの成長を止めるためには免疫の力が必要です。
犬ががんになってしまったのは免疫の働き・免疫システムに異常が発生したためがんを見つけられなかったり攻撃力が弱くなってしまったからです。
既にがんを患ってしまっていても、免疫がしっかり働くようにできれば、無尽蔵にがんが増えてしまうのに歯止めをかけることができます。
ご愛犬の免疫システムを成長に戻すための試みとして、コルディをご利用下さい。
コルディで免疫対策をしご愛犬の免疫がしっかり働いてくれるようになれば、きっとがんとの共存も可能になると思います。
どこまで反応するかわかりませんが、少なくとも食欲がでて元気を取り戻せる可能性は十分あります。
よくあるご質問
- 犬の肝臓がんとは何ですか?初期症状はありますか?
-
肝臓にできる悪性の腫瘍のことを肝臓がんと言います。肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれており、がんが発生しても初期段階では症状が現れにくいため、発見が遅れがちです。症状が現れる頃には進行しているケースが多く、疲れやすい、元気がない、食欲がない、お腹に水が溜まる(腹水)、血液検査で肝臓の数値が悪化するなどの症状が見られることがあります。
- 犬の肝臓がんにはどのような種類がありますか?
-
大きく分けて、肝臓自体からがんが発生する「原発性肝臓がん」と、他の臓器のがんが肝臓に転移した「転移性肝臓がん」があります。原発性肝臓がんには主に、以下のものがあります。
- 肝細胞がん(最も多く、原発性の約半数を占める)
- 肝内胆管がん(胆管に発生)
- 肉腫(血管肉腫など、肝臓の血管などに発生)
- カルチノイド(神経内分泌由来のがん)
- 犬の原発性肝臓がんの主な原因は何ですか?
-
人間の場合は肝炎ウイルスが主な原因ですが、犬や猫では化学物質などが原因で肝細胞が慢性的な炎症を起こし、がん化することが知られています。農薬、薬剤(抗がん剤、抗生物質、ステロイドなどの長期使用)、食品添加物(防腐剤、着色料、保存料)、塗料、化学薬品、排気ガス、洗剤などが体内に慢性的に取り込まれることがリスクを高めると考えられています。タバコの煙(受動喫煙)もがん発生率を高める可能性が報告されています。
- 転移性肝臓がんの原因は何ですか?
-
転移性肝臓がんは、体の他の部位に発生した「原発のがん」が肝臓に広がったものです。原因となる原発のがんは様々で、胃、腸、胆嚢、胆管、膵臓などの消化器系のがんや、乳腺腫瘍、肺がんなどが肝臓に転移することがあります。また、血管肉腫、リンパ腫、骨髄腫、肥満細胞腫、メラノーマなども肝臓に転移しやすいがんです。血流の滞りや体温の低下は転移のリスクを高める可能性があるため、体を冷やさないことも大切です。
- 肝臓がんの診断はどのように行われますか?
-
血液検査(ALP, AST, ALT, γGTPなどの肝酵素測定)、尿検査、画像検査(超音波(エコー)検査、レントゲン検査、MRI検査、CT検査)、そして確定診断のための肝生検(肝臓組織の一部を採取して調べる病理組織検査)などが行われます。血液検査で異常が見つかった場合に、より詳細な画像検査が推奨されることが多いです。
- 肝臓がんの主な治療法には何がありますか?
-
主な治療法として、外科手術、抗がん剤治療、放射線治療があります。これらに加えて、代替療法、食事療法、免疫ケアなども、状態に応じて検討されることがあります。
- 肝臓がんの手術はどのような場合に行われますか?
-
がんが肝臓の一つの葉に限局しており、周囲への広がり(浸潤)が見られない塊状の腫瘍の場合、がんを完全に取り除くことを目指す根治的な外科手術が検討されます。ただし、がんが広範囲に広がっている場合や、浸潤しやすいタイプの癌(例:カルチノイド)、全身状態が悪い場合には手術が適用できないこともあります。症状緩和を目的とする姑息的な手術が行われることもあります。
- 抗がん剤治療は肝臓がんに効果がありますか?
-
抗がん剤治療は、がんを完全に治す(完治させる)目的というよりは、一時的にがんを小さくしたり、進行を遅らせたりすることを目的として行われることが多いです。肝動脈塞栓療法や肝動注化学療法といった特殊な治療法を行う動物病院もありますが、一般的に抗がん剤だけで肝臓がんを完治させることは困難とされています。
- 放射線治療はどのように行われますか?注意点は?
-
手術と併用されたり、放射線治療単独で行われたりすることがあります。ただし、放射線に対する反応は個体差があり、治療には全身麻酔が必要となるため、麻酔薬による体への負担は避けられません。特に高齢の犬や肺に疾患がある犬の場合、麻酔のリスクが高まるため、慎重な判断が求められます。
- 代替療法とは何ですか?どのような場合に検討されますか?
-
代替療法は、手術、抗がん剤、放射線治療といった従来の治療法に代わる、あるいはそれらと併用される治療法です。一般的に体への負担が比較的軽いものが多く、従来の治療のリスクが高い場合(合併症があるなど)、手術後の再発予防、手術ができない症例、体力が低下している時などに検討する意義が大きいと考えられます。
- 肝臓がんの治療を受ける際に大切なことは何ですか?
-
手術、抗がん剤治療、放射線治療には、それぞれメリットとデメリットがあります。治療によってQOL(生活の質)が向上することもあれば、逆に低下してしまう可能性もあります。ご愛犬の状態を一番良く把握しているのは飼い主様です。獣医師とよく相談し、ご愛犬の体力やがんの状態、そしてQOLを考慮して、治療方針を決定することが重要です。
- 肝臓がんの犬の食事で最も重要なことは何ですか?
-
がん細胞は、主なエネルギー源としてブドウ糖(糖質)を利用します。そのため、普段の食事に含まれる糖質(炭水化物やデンプン質、芋類など)をできるだけ減らすことで、がんの成長にブレーキをかけることが期待できます。これはすぐに始められ、体への負担や副作用のリスクもほとんどない、食事療法の基本となります。
- 肝臓がんの犬にはどのようなタンパク質を与えるべきですか?
-
炭水化物・糖質を制限する一方で、体力を維持するために「適度なタンパク質」を与えることが推奨されています。ただし、肝機能が著しく低下している場合にはタンパク質の代謝産物(アンモニアなど)が体に悪影響を及ぼす可能性もあるため(肝性脳症のリスクなど)、タンパク質の量については、必ず獣医師の指導のもと、個々の状態に合わせて調整することが重要です。
一方、タンパク質を分解したアミノ酸を積極的に与えることで肝臓に負担をかけずに必要な栄養素を補うことができます。
参考記事
- BCAAとは何ですか?肝臓がんの犬に与えるメリットは?
-
BCAA(分岐鎖アミノ酸)はアミノ酸の一種です。BCAAなどのアミノ酸製剤を併用することで、肝臓に負担をかけずに、不足しがちなタンパク質(アミノ酸)を効率よく補うことができるとされています。
- 肝臓がんの食事療法で他に推奨されるものはありますか?
-
がん対策として、ビタミン類を積極的に摂取することが推奨されています。また、抗炎症作用などが期待されるクリルオイルの利用も提案されています。具体的な食材については、「ペットだって医食同源-がんに負けないための食材」リストなども参考に、獣医師と相談しながら進めることが大切です。
- 食事療法だけでがんは治りますか?
-
食事を変えるだけでがんを治すことはできません 。しかし、がんの成長に不可欠な糖質を制限するなど、食事内容を見直すことで、がんの進行速度を抑えたり、体力を維持したり、貧血やアルブミン値などを改善させたりする効果が期待できます。食事療法はご家族の協力が不可欠ですが、治療のベースとして非常に重要と考えられています。
- 肝臓がんと闘う上で、なぜ免疫ケアが重要なのですか?
-
肝臓がんと闘う上で最も大切なことの一つが、免疫を整えることです 。手術や抗がん剤治療を行う場合でも、それらの治療ができない場合でも、免疫を整えることは予後の改善につながる可能性があります。免疫がしっかり働くことで、がんの成長を抑制したり、感染症を防いだりする効果が期待できます 。
- コルディはどのように作用すると考えられていますか?
-
コルディは、ペットの免疫を調整する(低下した免疫を高め、過剰な免疫を抑制する)働きが期待されています。この免疫調整作用により、がんやその他の難治性疾患(猫のFIPやFeLVなど)の改善、あるいは病気がちな子の免疫対策やアンチエイジングなどに役立つ可能性が研究されています 。
- コルディはどのような犬に推奨されますか?
-
高齢で体調が心配なペット、普段から体が弱く免疫力を高めたいペット、がん治療を受ける、または治療中のペット、獣医師からこれ以上の治療は難しいと言われたペット、余命宣告を受けたペットなどに、免疫対策の一つとして検討されることがあります。動物病院のがん治療にコルディを併用することで、予後が改善する可能性も考えられています。
- コルディの安全性は確認されていますか?副作用は?
-
コルディは、GLP(優良試験所基準)適合機関で安全性試験(急性毒性試験、亜急性毒性試験、遺伝毒性試験など)が実施され、安全性が確認されています。また、GMP(適正製造規範)認定を受けた工場で、クリーンな環境下で培養され、DNA検査による品質管理も定期的に行われています。競走馬のドーピング検査もパスしています。提供された資料の範囲内では、副作用に関する記述は見当たりませんでした。
- 犬の肝臓がんの予後はどうですか?
-
肝臓がんの予後は、がんの種類、進行度(ステージ)、治療法、犬の全身状態などによって大きく異なります。例えば、肝細胞がんでも外科手術で完全に取り切れた場合の予後は比較的良好とされますが、肝内胆管がんや血管肉腫などは浸潤性が高く、予後が良くないことが多いと言われています。転移性肝臓がんの場合は、元の(原発の)がんの種類や進行度によります。個々の状況について、詳しくは獣医師にご確認ください。
- 肝臓がんを予防するために、日常生活で気をつけることはありますか?
-
犬や猫の肝臓がんは、化学物質などによる慢性的な肝臓への刺激や炎症が原因となることがあります。そのため、農薬、特定の薬剤の長期使用、食品添加物、排気ガス、洗剤、タバコの煙など、発がん性が疑われる物質への暴露をできるだけ避けることが大切です。また、バランスの取れた食事、適度な運動、定期的な健康診断(血液検査など)による早期発見も重要です。犬伝染性肝炎に対するワクチン接種も予防につながります。
- 肝臓の数値(ALP, AST, ALTなど)が悪いです。どのような原因が考えられますか?
-
血液検査での肝酵素(ALP, AST(GOT), ALT(GPT), γGTPなど)の上昇は、肝臓がんの可能性も示唆しますが、それ以外にも肝炎、肝硬変、門脈シャント、胆石や胆泥、胆嚢粘液嚢腫などの胆嚢疾患、あるいは他の病気や薬剤の影響など、様々な原因が考えられます。症状だけでは判断が難しいため、原因を特定するには、超音波検査などの画像診断や追加の検査が必要です。
- プラセンタは肝臓に良いのですか?
-
国産SPF豚由来のプラセンタキス末(プラセンタ製品の一種)が、肝機能が低下した犬の肝臓数値改善に役立ったという報告例があります。肝臓機能の回復効果が期待できる可能性が示唆されています。
- クリルオイルは犬の健康に役立ちますか?
-
クリルオイルには、抗炎症作用や認知機能の維持(認知症予防)などが期待できるとされています。
犬・猫の肝臓がん・肝細胞がん・肝臓腫瘍に関する参考記事
このページをご覧いただいているのは犬の肝臓が心配な方や既に肝臓の病気を患ってしまっている方だと思います。
ご愛犬が肝臓の病気にならないように気を付けるべきこと、犬の肝機能が悪化・肝臓の働きが低下した時の症状、犬の肝臓の状態を確認するための血液検査・検査項目、肝臓の働きが悪くなるのを予防する方法、肝臓の働きを維持するためのヒントなどについてまとめましたので、宜しければ参考になさってください。
監修獣医師:林美彩 所属クリニック:chicoどうぶつ診療所

代替療法と西洋医学、両方の動物病院での勤務経験と多数のコルディの臨床経験をもつ。 モノリス在籍時には、一般的な動物医療(西洋医学)だけでは対応が困難な症例に対して多くの相談を受け、免疫の大切さを痛烈に実感する。
ペットたちの健康維持・改善のためには薬に頼った対処療法だけではなく、「普段の生活環境や食事を見直し、自宅でさまざまなケアを取り入れることで免疫力を維持し、病気にならない体づくりを目指していくことが大切である」という考えを提唱し普及活動に従事している。
所属:

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう