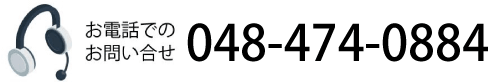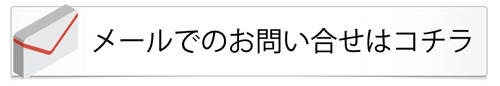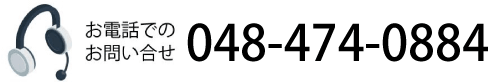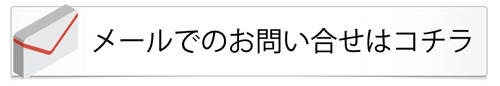目次
犬のコアワクチンについて
致死率の高いウイルスの予防となるコアワクチン。
このページでは、犬のコアワクチンが予防するウイルス病がどのような病態を起こすのかをまとめていきます。
犬ジステンパーウイルス
感染経路
感染犬の目やにや鼻汁、唾液、尿や便、またこれらが付着した物から、他の犬に感染を引き起こします。
特に空気が感染する冬場に感染が広がりやすいと言われています。
潜伏期(ウイルスに感染してから症状が出るまでの時期)は数日~2週間程度です。
人には感染しません。
症状
①感染後約1週間~2週間
40℃以上の発熱が数日続いた後、一旦平熱に戻りますが、再び40℃以上の発熱を引き起こします(二峰性発熱と呼ばれます)。
食欲不振や元気消失、嘔吐・下痢などの消化器症状、咳、目やにや結膜炎などの症状も見られます。
血液検査では白血球数の大幅な減少(3,000~5,000/ml以下)が見られます。
幼弱な犬の場合、全身状態が悪化し死亡することもあります。
②感染後3週間~
上記①の期間を乗り切ったあと、流涎(よだれ)や口をクチャクチャさせるような仕草、チックと呼ばれる不定期的な皮膚の痙攣が見られます。
咳や気管支炎、肺炎などの呼吸器症状を併発することが多く見られます。
結膜炎などの影響から視力低下を引き起こすこともあり、視力低下による怯えから錯乱状態に陥ってしまったり、歩行異常を呈する場合もあります。
皮膚は紅斑が見られたり、水疱や膿疱が形成されることもありますが、ハードパットという肉球の肥厚が見られるのが特徴です。
最終的には、痙攣や麻痺などの神経症状が現れ、致死率は90%と言われています。
これらを乗り切って回復した後でも、神経症状が残るケースも少なくありません。
治療
有効な治療法はなく、ウイルスの抑制と細菌の二次感染を防ぐ事が重要となります。
ウイルスの抑制にはインターフェロン、細菌の二次感染防止に抗生剤が用いられます。
その他、症状の緩和のために吐気止めや下痢止め、抗けいれん薬なども用いられます。
全身状態の底上げのために、補液や栄養補給で体力を維持し、免疫力が回復することで、ウイルスを抑え込むことが出来ます。
犬アデノウイルス(犬伝染性肝炎)
感染経路
感染犬のくしゃみや鼻汁、唾液から、他の犬に感染を引き起こします。
症状は軽度~重度と様々で、成犬の場合は感染しても症状が起きないこともありますが(不顕性感染と言います)、ワクチン接種をしていない子犬では致死的状態に陥ることが多いウイルス病です。
回復した犬の場合、ウイルスが腎臓に残るため、数ヶ月~数年は尿にウイルスが含まれるため注意が必要です。
潜伏期は数日~10日程度です。
人には感染しません。
症状
①劇症型(突然致死型)
子犬で多く見られます。
ウイルスは消化器粘膜から感染するので、激しい腹痛、吐血、血便などの消化器症状が見られます。
40℃以上の発熱を起こした後、虚弱状態に陥ります。
多くの場合、感染後12~24時間以内に死亡します。
②軽症型
40℃程度の発熱と鼻汁、咳、食欲不振、元気消失、軽度の目やにが見られます。
③重症型
40℃程度の発熱後、肝臓に起きた炎症が原因で肝機能の低下が見られます。
肝機能の低下により、肝性脳症(肝臓で処理されるはずのアンモニアが大量に生じることで起こる神経症状)、沈鬱、昏睡、痙攣などの神経症状や、血液凝固機能の低下からの出血傾向、黄疸、腹水貯留、肝臓の肥大による腹部膨満が見られることもあります。
その他、咳や口内炎、結膜炎なども見られます。
回復期では、角膜が青白く濁ってみるブルーアイ(片側のみに起こることが多い)が見られます。
ブルーアイは通常数週間で回復していきますが、混濁が残る場合や、時折緑内障や角膜潰瘍に進行してしまう場合もあります。
④不顕性型
免疫力が正常に働いている成犬の場合は、感染しているのに何の症状も起こらない『不顕性』と言う状態になります。
治療
有効な治療法はなく、ウイルスの抑制と細菌の二次感染を防ぐ事が重要となります。
ウイルスの抑制にはインターフェロン、細菌の二次感染防止に抗生剤が用いられます。
また、肝機能を補うために、補液や肝庇護剤の投与も行われます。
全身状態の底上げのために、補液や栄養補給で体力を維持し、免疫力が回復することで、ウイルスを抑え込むことが出来ます。
犬パルボウイルス2型
感染経路
感染犬の唾液、尿や便から他の犬に感染を引き起こします。
乳汁によっても感染が起きるため、母体がこのウイルスを持っている場合には、子犬にも感染します(母子感染)。
また、胎盤を通じて感染が起きた場合には流産、生まれてきた子犬は心不全を起こすことがあります。
人には感染しません。
症状
①腸炎型
母犬からの移行抗体が消える生後6~16週頃の子犬で発症することが多い病態です。
元気消失、食欲不振、発熱、軟便や下痢(血便)・嘔吐などの消化器症状が見られます。
ウイルスが腸粘膜を破壊して、体内に侵入すると病状は悪化、毒素性ショックや敗血症に陥り、高確率で発症から1~2日以内に死亡します。
②心筋炎型
胎内感染や生後1週間以内に感染した場合に発症します。
初乳を飲んでいないなど、母犬からの移行抗体を持っていない子犬の場合、3~8週齢で突然の呼吸困難や脱水症状、非化膿性心筋炎(細菌感染を起こしていない心筋炎)を起こし、最悪の場合死に至ります。
治療
有効な治療法はなく、ウイルスの抑制と細菌の二次感染を防ぐ事が重要となります。
ウイルスの抑制にはインターフェロン、細菌の二次感染防止に抗生剤が用いられます。
全身状態の底上げのために、補液や栄養補給で体力を維持し、免疫力が回復することで、ウイルスを抑え込むことが出来る可能性が高まりますので、積極的に免疫対策を取り入れてみてください。
狂犬病
感染経路
感染犬の唾液に含まれるため、感染犬の咬傷から感染します。
潜伏期は2~6週間程度ですが、咬まれた部位や咬まれた動物の抵抗性、ウイルスの量などで潜伏期間の長短が変わります。
人を含むすべての哺乳類に感染します。
症状
①狂躁型
過剰な興奮状態・凶暴化が見られ(病名の通り、『狂犬』状態となる)、異食(小石や糞など)を呈することもあります。
通常この状態が2~4日続いた後、痙攣・運動失調などの神経症状(麻痺状態)となり、1~2日で死亡します。
狂犬病感染の80~85%が狂躁型によるものと言われています。
②麻痺型(沈鬱型)
凶暴性を示さない珍しい病型です。
頚部から上の筋肉に麻痺が生じるため、食餌や飲水が困難となり、脱水、削痩を起こします。
この麻痺が全身に進行すると、意識不明・昏睡が起こり、1週間以内に死亡します。
治療
治療法はなく、発症が確認された場合には安楽死となります。
発症はしていなくても、感染の疑いがある場合には係留し、経過観察を行います(最長180日間)。
また、日本では咬傷事故を起こした動物は狂犬病感染の有無を確認するため、捕獲後2週間の係留観察が義務付けられています。
日本は世界でも数少ない狂犬病清浄国ですが、いつ国内にウイルスが入ってきてもおかしくありません。
狂犬病の国内動物での発症例は、昭和32年以降見られていません。しかし、2013年7月には台湾でイタチアナグマが狂犬病ウイルスに感染していたことが確認されています。
また、2006年11月にはフィリピンに渡航していた日本人男性2人が帰国後に発症し死亡していますし、狂犬病流行地のロシアとの貿易が多い北海道には、ロシア船から不法上陸した犬の存在も確認されています(不法上陸した犬が狂犬病にかかっていたか否かは定かでありません)。
狂犬病が日本に入ってきても感染を広げないためには、予防接種をするしか方法はありません。
もちろん、ワクチン接種の大原則は『健康な個体への接種』ですが、ご自身の判断での未接種は危険です。
かかりつけの獣医師の診断のもと、狂犬病予防接種が可能か否かを判断していただいてください。
以上のように、ウイルス病の治療法は確立されておらず、体力維持や二次感染防止のための抗生剤投与がメインとなります。
ウイルス病にかからないためには、ワクチン接種はもちろんですが、一番は抵抗力=免疫力を付けておくことです。
免疫対策をして穏やかに過ごす
ワクチン接種後は免疫が乱れてしまいますので、しっかりと免疫対策をしてあげてください。
コルディ研究室ではコルディがワンちゃんの免疫を整え病状の改善につながるのか研究を進めています。
ご不明な点がございましたら、お問合せ下さい。
監修獣医師:林美彩 所属クリニック:chicoどうぶつ診療所
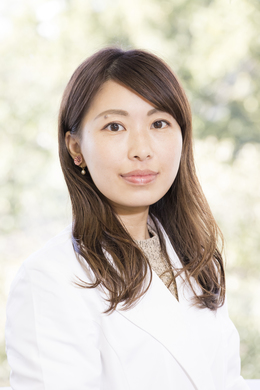
代替療法と西洋医学、両方の動物病院での勤務経験と多数のコルディの臨床経験をもつ。 モノリス在籍時には、一般的な動物医療(西洋医学)だけでは対応が困難な症例に対して多くの相談を受け、免疫の大切さを痛烈に実感する。
ペットたちの健康維持・改善のためには薬に頼った対処療法だけではなく、「普段の生活環境や食事を見直し、自宅でさまざまなケアを取り入れることで免疫力を維持し、病気にならない体づくりを目指していくことが大切である」という考えを提唱し普及活動に従事している。
所属: