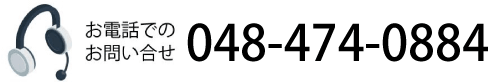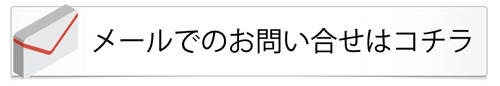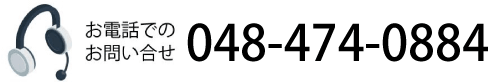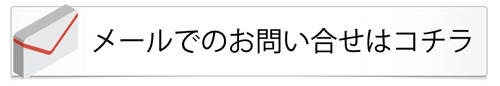肝臓病でお腹が張る犬猫に ― 腹水を悪化させない日常ケアと観察のポイント
目次
今日からできる基本ケア:腹水を悪化させないための3つの習慣
肝臓疾患が進行すると、犬や猫の体に腹水(ふくすい)がたまることがあります。腹水は病気そのものではなく、肝臓や血液の流れに負担がかかっているサインです。早期に気づき、日常でできる観察とケアを続けることで、悪化を防ぐことができます。
朝晩のルーティン:体重・お腹・足のチェック
- 体重測定:毎日ほぼ同じ条件(食前・排尿後)で行う。1日で200〜300g以上の増加が続く場合は注意。
- お腹の張り:形の変化を手で軽く触って確認。
- 後肢のむくみ:写真で比較すると分かりやすい。
食事のルール:塩分と水分のバランス
- 塩分過多は体内の水分保持を強め、腹水を悪化させる可能性があります。
- 療法食を与えている場合は、他のおやつや人間の食べ物を控える。
- 清潔な水をいつでも飲める環境を維持する。飲水量の急減も観察ポイント。
寝る姿勢と快適な環境
お腹が張ると仰向けがつらくなり、呼吸が浅くなることがあります。ベッドや毛布を少し傾けて胸を高くする姿勢をとると、呼吸が楽になります。冷えは腹水を悪化させる要因になるため、冷暖房の調整も重要です。
腹水がたまる仕組みを1分で理解
肝臓が傷むと血液がうまく流れずに門脈圧(もんみゃくあつ)が上昇します。その圧が高まると血液中の水分が血管外へにじみ出て、お腹の中にたまります。さらに、肝臓で作られるアルブミンというたんぱく質が減ると、体が水分を保持できなくなり、腹水やむくみが起こります。
観察と記録:早く異変をつかむ3つの指標
① 体重の変化
毎日同じ時間に測定し、1週間で5%以上の増加が見られたら獣医師に相談を。
② お腹のサイズ
胴まわりを柔らかいメジャーで測り、数値をスマホに記録。毛量が多い犬では、触った感触の変化を重視します。
③ 尿の回数と色
利尿薬を使用している場合でも、1日4〜6回の排尿が目安です。尿が濃くなったり極端に減った場合は、脱水や腎機能低下の可能性があります。
食事と水分の考え方:無理なく続けるポイント
塩分量を意識する
療法食以外のトッピングは控え、塩分を含むおやつ(チーズ・ハムなど)は避けましょう。与える場合は総摂取量の5〜10%以内に抑えるのが目安です。
水分摂取
基本は自由飲水が理想ですが、飲みすぎる場合は器を一時的に分けて管理します。制限は獣医師の指示に従い、自己判断では行わないようにします。
飼い主の食生活にも意識を
飼い主の減塩を意識することで、ペットの食事管理も自然に整います。
利尿薬と上手につきあうために
投与時間の工夫
犬猫でも利尿薬は朝の投与が基本。日中に尿を出すことで夜の頻尿を防げます。ただし、投薬時間は獣医師の指示に従ってください。
気をつけたいサイン
- 水を異常に欲しがる
- ふらつきや脱力
- 筋肉のけいれん
これらは電解質バランスの乱れを示すことがあり、早めの受診が必要です。
治療の進行と外来でできること
腹水が多い場合、病院で腹水穿刺(ふくすいせんし)という処置を行うことがあります。お腹に針を刺して溜まった液体を抜く方法で、犬猫では鎮静下で安全に実施されます。再発することもありますが、原因疾患のコントロールができれば腹水の量を減らせるケースもあります。
すぐに受診すべき危険サイン
- お腹が急に膨らみ、呼吸が浅い
- 発熱やぐったり感がある
- 白目・歯ぐきが黄色い(黄疸)
- 嘔吐や黒色便が見られる
これらは感染症や出血、肝機能悪化の可能性があり、夜間でも連絡を取ることが大切です。
飼い主ができるサポートと家族の協力
記録を共有する
スマホやノートに体重・尿・食事量をメモし、家族や動物病院と共有します。「いつ」「どんな変化があったか」を残しておくことで、治療方針が立てやすくなります。
環境の工夫
- 足腰の弱い子には滑らないマットを敷く
- トイレやベッドを移動しやすい位置に置く
- 水皿の高さを胸の位置に合わせる
心のケア
食欲が落ちたときでも、飼い主の声かけや触れ合いが回復の支えになります。「昨日より少し元気」「今日はよく飲めた」など、小さな変化を前向きに捉える姿勢が大切です。
よくある質問
腹水は治るの?
原因となる肝臓疾患が改善すれば、腹水が減ることはあります。ただし慢性疾患の場合は、うまく付き合う管理が基本になります。
利尿薬はずっと続けるの?
状態によって量を調整します。自己判断で中止せず、定期的な血液検査で確認が必要です。
食事制限はどこまで必要?
療法食を中心に、塩分や高脂肪を避けることが基本です。嗜好性を保つ工夫(温める・水分を加えるなど)で、無理なく続けることができます。
まとめ
犬や猫の腹水は、肝臓の負担を知らせるサインです。早期に気づき、体重・食事・尿の変化を「見える化」して獣医師と共有することが、再発を防ぐ最善の方法です。日々の小さなケアの積み重ねが、ペットの快適な生活を支えます。
当研究室では、コルディを投与することで免疫調整ができるのか、QOL(生活の質)の維持・改善ができるのか、癌への効果が期待できるのか研究を行っています。
ご不明な点がございましたら、お問合せ下さい。
監修獣医師:林美彩 所属クリニック:chicoどうぶつ診療所

代替療法と西洋医学、両方の動物病院での勤務経験と多数のコルディの臨床経験をもつ。 モノリス在籍時には、一般的な動物医療(西洋医学)だけでは対応が困難な症例に対して多くの相談を受け、免疫の大切さを痛烈に実感する。
ペットたちの健康維持・改善のためには薬に頼った対処療法だけではなく、「普段の生活環境や食事を見直し、自宅でさまざまなケアを取り入れることで免疫力を維持し、病気にならない体づくりを目指していくことが大切である」という考えを提唱し普及活動に従事している。
所属: